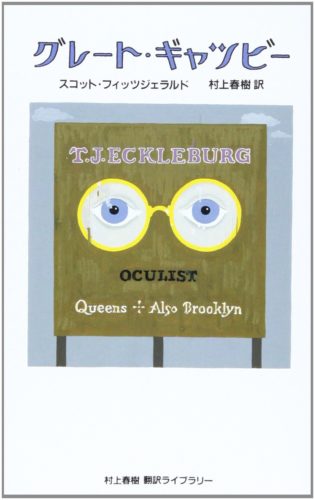
遅ればせながら村上春樹の書いたものを読んでいます。
前回読んだ「走ることについて語るときに僕の語ること」の中に翻訳中の「グレート・ギャツビー」の小説について、29歳でどうしてこのような深い内容の小説が書けるのだろうか。 天才というに以外に言いようがないというようなことが書いてあったこが、『グレート・ギャツビー』を読むことになった直接のきっかけでした。
『グレート・ギャツビー』はスコット・フィッツジェラルドが1924年に書いたものであり、舞台は1922年に設定されています。
古典の部類に入る長編小説としては少し短い>『グレート・ギャツビー』は村上春樹が出会ったなかで重要な作品であり、この本を読まなかったら、自分の書く小説も違ったものになっていたかもしれないという。
そしてその翻訳で「古典ではなく現代の小説とすることにした」と書いているためか、私にとっては分かりにくいところがほとんどなく、すんなりと心にな入ってきて中断するのが難しい作品でした。
スポンサーリンク
『グレート・ギャツビー』のあらすじ
中西部の都市で少しは名の知れた出であり、イェール大学を卒業後戦争に従軍し、休戦ののち故郷へと帰ってきたニック・キャラウェイは証券の勉強をしてみようと思い、ニューヨーク市から20マイル離れた郊外の1軒屋を借ります。
その隣の大邸宅では、ギャツビーの家であり毎週土曜日の夜に華やかなパーティーを開いて見知らぬ人が大勢集まってにぎやかな夜を楽しんでいました。
その場所は小さな湾になっている先端で高級感にはかけていたが、ちっぽけな湾を隔てた対岸は高級住宅地イースト・エグで、そこにはニック・キャラウェイの大学時代の友人のトム・ブキャナンとその妻で再従弟の子供に当たるデイジーの家があり、息を飲むような派手な暮らしをしていました。
その家に夕食ともにするために訪れたことからこの物語は始まります。
トム・ブキャナンは大学のフッドボール史上最もパワフルなエンドの一人として全米にその名を轟かせたが、そのあとは何をしてもしりすぼみという風だったが、同じ年代の人間にそんな暮らしができるなんて実感がわかないとニック・キャラウェイは思うのです。
そこに同席していてミス・ベイカーから、トムにニューヨークに愛人がいることを教えられたが、その後その愛人は自動車修理工場のウィルソンの妻、ミセス・ウィルソンであることを知りそのアパートでその妹や写真家なとと飲み明かすというめぐりあわせをすることになりました。
デイジーの友人であるミス・ベイカーにより、中尉だったころのギャツビーはデイジーに思いを寄せていたが、ギャッピーが出征してしまった後、あまり良いうわさがなかったデイジーが、大金持ちのトム・ブキャナンと結婚して女の子にに恵まれていました。
ニック・キャラウェイは隣の公邸で派手なパーティーをしているギャツビーは、昔のデイジーの恋人であり、デイジーを探し当てて対岸に住み、デイジーがいつか来るのではないかの期待でほとんど知り合いでもない人を招待してパーティーを開いていたということを知ることになります。
ミス・ベイカーとニック・キャラウェイがデイジーと知り合いであることを知り、中立ちを頼んでデイジーと再開することが出来たギャツビーは、無我夢中になり5年の歳月を埋めようとするのですが、ギャツビーの純粋さほどのかけらもデイジーは持っていませんでした。
トム・ブキャナンから、デイジーを奪うことが出来ると見えた時、ギャツビーと同乗していてデイジーが運転していた車が、トム・ブキャナンの愛人であるミセス・ウィルソンをひき逃げしてしまいます。
ギャツビーが止めるのも聞かずにものすごくスピードで逃げてしまったデイジーは何事もなかったように、トム・ブキャナンと元の生活に戻り、心配しているギャツビーに電話さえもかけてきませんでした。
その後、ウィルソンはトム・ブキャナンを打つつもりで尋ねたが、それはギャツビーの車だと教えられ、ウィルソンはギャツビーの家を尋ねあてギャツビーを殺し自分も自殺してしまいます。
ギャツビーのお葬式には、ニック・キャラウェイとその貧しい農民のの父親、パーティーに来ていた1人のほかは誰も参列しませんでした。
この事件は大きく報道されたのですが、純粋なギャツビーの気持ちを引き裂いたまま、自分が犯した罪もなかったようにデイジーからは何の連絡もありませんでした。
ニック・キャラウェイは人をかき回しておいて後始末をさせる思慮を欠いた人間として、トム・ブキャナンとデイジーの思慮のない行為に何とも言いようのない気持ちになり、故郷へと戻っていきました。
ニック・キャラウェイは書き出しで、得体の知れなかったギャツビーの心根を次のように分析しています。
実のところギャッピーは僕が「このようなものは絶対に我慢ならない」と考えるすべてを、そのまま具現したような存在だった。もし人格というものが、人目につく素振りの途切れない連続であるとすれば、この人物は確かに驚嘆すべきものがあった。人生のいくつかの約束に向けて、ぴったりと照準を合わせることのできる研ぎ澄まされた感覚が、彼には備わったいたのだ。1万マイル離れた場所に起こった地震にさえ反応する精緻な計器に繋がっているかのように、この反応の鋭敏さは「『創造的性格」という名で呼ばれる上っ面だけの感受性とは、全く別のものである。それは彼に尋常でない希望を抱かせ、強い夢想へと駆り立てた。そのような心を、僕は今までほかの誰の中にも見いだすことが出来なかったし、これからもおそらく目にすることはあるまい。そう-ギャッピーはは最後の最後に、人としてまっすぐであったことを僕に示してくれた。果たされることなく終わった哀しみや、人の短命な至福に対して、僕が一時的にせよこうして心を閉ざすことになったのは、ギャッツビーをいいように食い物にしていた連中のせいであり、彼の夢の航跡を汚すように浮かんでいた、醜い塵芥のせいなのだ。
上の文章は第1章に書かれているもので、作者の言いたいことがすべて述べられえいることになりますが、この文章はその後の物語を読んで納得できるものになっています。
私は『グレート・ギャツビー』を村上春樹の翻訳でしか読んだことがないし、映画も見たことがないが、それほど多く読んできたわけでもない本の中でかなり深く心を奪われた本の1冊になったことをうれしく思いました。



