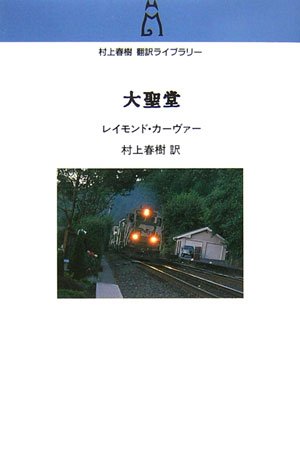
レイモンド・カーヴァーの作品を読むにあたって、レイモンド・カーヴァーのことを書いてあるいくつかの文章を読みました。
そのあとに読んだ短編集は『愛について語るときに我々の語ること』で、『大聖堂』が2冊目の短編集です。
50歳で肺がんにより亡くなっていますので、本格的に小説を書いたのはそれほど長い期間ではなかったようですが、それらの作品の多くは自らの体験によって紡ぎだされた生きることの切なさ、悲しさ、温かさをさりげなく伝えています。
『愛について語るときに我々の語ること』の短編集では、最後に読み手がポンと投げ出されるように感じることもありましたが、『大聖堂』は温もりが感じられます。
若く結婚して子供が生まれ、家族とうまくいかなくなりアルコールに依存していたレイモンド・カーヴァーがアルコールを止め、離婚した後にテス・ギャガラーと出会い心の安定を得たことが作品にも影響しているのでしょうか。
スポンサーリンク
『大聖堂』の読後感
『愛について語るときに我々の語ること』のレイモンド・カーヴァーの短編の鋭い切り口に感動して読んだのですが、『大聖堂』は寂しさの中に暖かな心が加わり灯を感じるような読後感でした。
日常の些細なことで、私たちは幸せにもなり不幸にもなりうるということをこの作品から学ぶことができます。
ほんの少しのボタンの掛け違いが、夫婦の関係、親子の関係にひびが入って取り返しのつかなくなるありようを私たちに教えてくれます。
そのような悲しい日常の中であっても『大聖堂』においてはその先に灯のようなかすかな光が見える作品が多くなっているのを感じて救われるような思いがします。
羽
主人公の私と妻が招待された友人の家で、醜い子供と奇妙なクジャクに出会いびっくりしますがその地に足が付いた家庭に感動して、自分たちもそのような家庭をつくろうとするが失敗してしまうという物語です。
あこがれていた子供も生まれるが、子供はずる賢く、妻は素敵だった長い髪を切って太ってしまい何もかも変わってしまったのです。
子はかすがいと言われるが、生きることはそれほど甘いことではなく、子供が生まれたことにより夫婦の関係が悪くなることもありうるということを示唆しているのだろうと思います。
カーヴァーの作品は、ほんの些細なことで自分自身さえ気が付かないように心は移り変わり、絶望にと変わってしまう心を書いていて、いつの間にか自分の心と向き合っているような思いになっているのを感じてしまいます。
醜い子供とクジャクと暮らす友人の幸せな家庭と、満たされていたはずの主人公の絶望感から多くを学ぶことができます。
ささやかだけで、役に立つこと
『愛について語るときに我々の語ること』には「風呂」という題名で収録されたものと同じバージョンですが、こちらの方がかなり長くなっています。
私は「風呂」を先に読んでいるわけですが、中途半ぱな最終章に違和感を覚えましたので、「ささやかだけで、役に立つこと」の方が絶対良いと思って読みました。
母親は子供の誕生日のケーキを頼みに入ったケーキ屋の主人はぶっきらぼうで愛想が悪かったが、子供の誕生日の月曜日に間に合うようにケーキを頼んできました。
月曜日の朝の登校時にその子は車にはねられてしまうが、子供が「大丈夫」と言ったことから車は走り去ってしまい、友達は学校に行ったが、その子は家に戻って、車にはねられたことを母親に話した後に意識を失ってしまいます。
救急車を呼び、その子の父親の勤務先に電話を入れて、病院で二人で付き添っているが子供の意識は戻らず、悪い予感を抱きながら付き添うことになります。
医者は、子供が目を覚ませば何ら問題がないと言い、昏睡状態ではないというが子供はいつまでも目を覚まさず嫌な予感だけが募るのですが、父親は一度家に帰って風呂に入り着替えてきます。
その時にケーキを頼んだパン屋からの電話があるが、パン屋は詳しいことを言わないので父親はその電話に不安を募らせます。
母親も夫の勧めに従って、自分がいなかったら子供が目を覚ますのではないかと家に帰るのですが、その時も電話があり不安を募らせます。
「風呂」はここで終わるのですが、「ささやかだけど、役に立つこと」はここからの続きがあります。
不安を募らせた妻は、病院に電話をするのですが、様態は変わらないと言われて、病院に戻ると目が覚めない理由が分からないので手術をするかもしれないということを聞かされます
その後、子供は目を開け父と母を見たが何も分からないようで、その直後に息を引き取ります。
なぜ亡くなったか調べるために子供を置いて家に帰った夫と妻は、親戚に電話を掛けるのですが、その後にパン屋から電話があり、やっと電話の主が分かり、ショッピングセンターに車で向かうことにします。
何も知らないパン屋と子供を亡くした夫婦が言いたいことを言ってぶつかった後に、子供が亡くなったことを言うとパン屋はびっくりしてそれまでの行動を詫び、2人に温かいパンをごちそうしてくれます。
何も食べずに、病院で付き添っていた夫婦はパンの暖かさに心が和んでいくのでした。
優しさを忘れていたパン屋と疲れ切っていた子供を亡くした夫婦はパンで心を通わすことができたのです。
下記のような言葉が心を温かくしてくれます。
何か召し上がらなくちゃいけませんよ」とパン屋は言った。よかったら、私が焼いた温かいロールパンを食べてください。ちゃんと食べて生きていかなきゃならんのだから。こんな時には、ものを食べることです。それはささやかですが助けになります」と彼は言った。
中略
彼は世の中の役にたつ仕事をしているのだ。彼はパン屋なのだ。彼は花屋にならなくてよかった思っている。花を売るよりは、人に何かを食べてもらう方がずっといい。
ぼくが電話をかけている場所
僕とJPはアルコール中毒療養所にいて、僕は2度目だがJPは初めてなのでおびえているが、プロントポーチで枯れ井戸に落ちたこと、煙突清掃人にになったいきさつを話しています。
井戸の中から見た風景は、訳者村上春樹の『ねじまき鳥クロニクル』の枯れ井戸から見た風景とだぶって見え生きることの寂しさのようなものを感じさせられました。
そのJPが友人の家で煙突清掃人の少女と出会い、恋と仕事を同時に得ることができて子供にも恵まれ、幸せに暮らしていましたが、大きなきっかけもないままにアルコールに溺れて行ってしまったと言います。
レイモンド・カーヴァーは、どんな幸せな人生もそのまま続くことはありえないし、日々の些細なことから人は変わるものだということをさらりと書いていくのです。
その変わり方は私であったり、子供であったり、身近な人であることを納得させてくれるようで、ひやりとさせられます。
そんな危うい愛の形を持つ人たちが集まっているのがこの療養所であり、それでも愛は力を持っています。
僕は最初の入所は妻に連れられてきましたが、2度目はガールフレンドに連れられてきたのですが、JPに妻のロキシーが会いに来て幸せそうにしているのを見た僕は温かな気持ちになります。
ガールフレンドに電話をかけてみようと決心をする最終行の「やあ、シュガー」と彼女が出たら言おう。「ぼくだよ」と映像のような文章で終わっています。
大聖堂
妻の昔からの友達の盲人が泊まりに来ることになったが、それまで盲人と付き合ったこともない夫はあまり歓迎していない様子です。
その盲人との一夜の様子、言って見れば私たちが一人の客を招き夕食を共にして、酒を飲み、テレビを見て過ごすというありふれた一夜の様子を書いているのですが、そのささやかな一夜でさえレイモンド・カーヴァーは見事に書いて、感動的です。
食事を終えて妻がソファーに寝てしまった後に大聖堂のテレビを見ていた二人は、盲人に大聖堂を説明することになりますが、信仰のない夫にはうまく説明することができません。
盲人から紙とボールペンを持ってくるように頼まれた夫は手を重ね合わせて、大聖堂を書き上げていくことになります。
絵心がないと思っている夫が盲人に励まされて書いた大聖堂は見事な出来で、盲人はそこから大聖堂を理解することができ、盲人と夫は心の中に大聖堂を描くことになるのです。
目が見える、見えないという現実を超えたところで私たち人間は心を通い合わすことができる感動を軽いタッチで描いているカーヴァーの短編はすごいとしか言いようがありません。
押しつけがましい表現がどこにも見当らず、こころに灯をともしてくれる『大聖堂』に出会ったことをとてもうれしく思いました。
この短編集は、私の大好きな小説のひとつとして何度も読み返すことになるのだろうと思いました。



