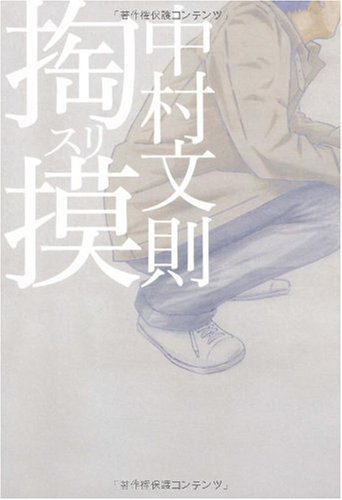
中村文則著『掏摸』は第4回大江健三郎賞受賞作であり、作者の代表作といっても良いと思います。
芥川賞受賞作家でもあり、『教団X』を先日読んでほかの作品も読んでみたいと思って選んだのが『掏摸』になります。
『教団X』の世界観にひかれて読むことにしましたが、一気に読み進むことができたのが、『掏摸』でした。
中村文則氏の作品が暗いというのが一般の読後感のようですが、この本もその範疇に入る作品であり、人間の持つ内面を描いていて、ドストエフスキーの罪と罰を思い出しながら読みました。
ドストエフスキーのような実在主義の作家と見た時に、この作品で何を言おうとしているのは、社会の矛盾であり、「信じる者は救われるか?といういう思い」が流れているいると思いました。
スポンサーリンク
『掏摸』 中村文則著ー神話に見られる絶対的な存在、運命の下で働く個人
裕福な人を狙って巧みな指さばきで掏摸をして生計を立てているのがこの作品の主人公なのです。
どのような生い立ちなのかは書かかれていませんが、子供のころから万引きをして食べなければ生きていけない境遇だった彼は違和感は感じていたようですが、罪悪感は感じていないようです。
しかし、少年に万引きをさせている母を見てその母子とかかわりを持つようになりますが、少年に掏摸の仕方を教えながらも、そのような生活はやめて施設に入ることを勧めるのは自分の生き方を肯定していないのでしょう。
生きるために子供のころから万引きをしてきた彼にとってはそれ以外の生き方がなかったとしか言いようがありません。
上手に立ち回ることができる人が得をして、正直に生きようとしている人に恵まれない人が多いのは世の常だと思っている私は、彼が子供のころから繰り返えし覚えた掏摸という特技で生きる方法しかなかったのかもしれません。
小さいころいつも遠くに塔があったと感じている主人公にとってその塔とは何だったのだろうか。
その塔の存在が、反社会的な万引きをしたり、掏摸をしたりする主人公の心に温かさを感じさせてくれたのは塔を見つめる心で、悪を働きながらも悪に染まりたくないという心だったのかもしれないと思いました。
子供だった頃、お店に入っておにぎりをポケットに入れるのだが、他人のものは手の中で、異物として重かったと感じる心と、外国製のきらきら光るおもちゃの自動車を盗んで、自分のものとした自動車もすぐに飽きて川に捨ててしまう心と重なっていて本当の喜びではないことを子供心に知っていたのです。
そのように成長した主人公は掏摸が反社会的にしろ、手先の器用さで狙って財布を掏ることがある一方、気づくことなく掏っている面を考えれば抜け出すことのできない性になっていたようです。
掏摸仲間というのがいるようで、その仲間が得体のしれない木崎という男をトップとする仲間に組み込まれていき、命令どうりにことが運んだ後に、主人公は東京を後にするが、しばらくして東京に戻って掏摸をしていた時にその仲間に戻されることになるのです。
世の中には逃れようのないことが起こるのが常であり、そのような立場に陥った時は自己判断さえも許されなくなってしまうようです。
このようなことは悪人ばかりの世界でなく、どんなところに身を置いていても自分が信じる道に行けなくなってしまうような強い力が働いているのは、政治の社会であっても、会社という世界であっても同じなのではないかと感じさせられます。
小説のように体までは殺されることがありませんが、心を殺して生きなければならないのは、善悪を超えたところで働いているのかもしれません。
逃げ場がなくなった主人公は、難題を突き付けられて、それをやり通しても、やり通さなくても殺されなければならないという運命を負うことになります。
それを織り込まれた生として木崎はとらえているのですが、宗教とも深いかかわりがあるのかもしれないと思うこともあります。
旧約聖書の神話に見られる絶対的な存在、運命の下で働く個人、という構図だと作者が言っていつことにもうなずけるものがあります。





