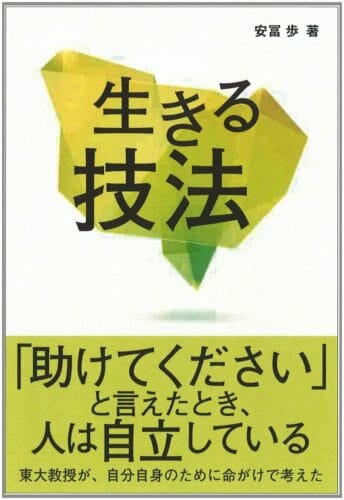
2019年の参議院議員選挙の時に、「子どもを守るということを、政治の原則にしよう」と東大教授である安富歩氏がれいわ新選組から立候補し、選挙運動をしているのをネットなどで何度か目にしたことがあります。
それまでも名前や写真は見たことがありますが、その時、れいわ新選組について書いている文章を読んで、(れいわ新選組には批判的な私だったのですが)私の心を捉える文章に興味をいだき、いつか著書を読んでみたいと思っていました。
その思いから読んだのが『生きる技法』です。私の元に届いた帯には「助けてください」と言えたとき、人は自立していると書いたありました。
アマゾンで安富氏の著書を見るとかなり高価なものが多く、読んでみたいと思いながらも、初めて読むにはためらうものも多かったのですが、その中でも『生きる技法』は私にも求めやすい価格であったために購入して早速読んでみました。
スポンサーリンク
『生きる技法』の内容と読後感
あまり多読とはいえないまでも若い頃から読書を趣味としている私の読後感は、とても素晴らしい本という印象でした。
私が今まで読んできたようなハウツー本とは、かなり異なっており、著者がそれまでの人生の中で、本当にもがき苦しみながら考え、それを裏付けるように、スピノザ、ガーンディー、孔子、親鸞、アリス・ミラー、アルノ・グリューン、エーリッヒ・フロム、マイケル・ジャクソン等の思想を元に心の格闘の中から生み出された著書で、過激であるとの思いもありますが、納得させられます。
1から8までをいくつかの命題に分けて書いており、その命題ごとに読者に問いかけています。
1 自立について
中村尚司さんという経済学者が、小学生の頃から「自立とは何か」と考え続け、60年間考えてようやく、「自立とは依存することだ」という答えに到達されたと言います。これは私も、そして多くの方が「依存から脱却しなければ」と思っているのではないかと言う驚きがありました。
著者も同じように思っておられて、それから脱却するのに10年くらいの歳月がかかったと書いています。子供の頃から母親に隷属し、結婚してからは妻に隷属していたと言います。
そんな折、中国に行くことになり、金をとらずに移植林をしている朱さんに出会い、無所有という戦略を活用した氏を調べて、「依存を通して自立する」と言うことが貨幣をもちいても可能であることを感じることができました。
それにより家を出て離婚を考えましたが、母から反対されるような軋轢の中で自殺まで考えたのですが、両親との関係を絶った時、自殺衝動は消え、配偶者にたいする恐怖心もきえたと言います。
凄まじい経験をなさったようですが、ハラスメントによって育てられ、妻のハラスメントを受けていたと言う著者の言葉は個人的なこと故、誰にでも分かることではないのかもしれません。
2 友達について
著者は自立するためにはまず親からの自立が大切であり、友達をたくさん得て依存することが大切だと説きます。友達は互いに尊重し合う人のことであり、勝手な像を押しつけることをしない創造的構えの人を選ぶようにします。
他人にいろいろと押しつけるようなことをする人と友達になると誰とも友達になることが出来ないと言います。しかし狭い世界の中に生きている私などはそれほど友達といえる人をもつことが出来ませんし、とても難しい命題のような気がします。
しかし、親からいろいろと押しつけられることもなく育ち、ある年齢には親に反抗しながら自由に育ったと思っている私はある程度の年齢からは親から自立していたと思っていますし、親から干渉を受けた記憶もないので、親子関係で悩む人のことを反対に理解できていません。
それよりも子供に対して親としての接し方の方が気になりますが、大学に入学して家を離れた後は一緒に生活することのない子供に対しては、相談されたこと以外は、ほとんどの場合口出しはしないようにしています。
我が家の子供も強いので、自分がいやだと思ったことは親には従わないし、反抗して来るし、早い段階で自立しています。それが普通のことだと思いながらも、親と子としては寂しい思いをするのは否めません。
いま、親子関係で悩んでいる人が多いようなので、親も子もこのような本を読んで考えたらよいのではないかと思いました。
私自身も子供とよい友達になっているという自信はありませんが、困ったときには子供も助けてくれるのでこのままの形で付き合っていきたいと思っています。
3 愛について
愛については、自愛と自己愛について述べています。
- 自愛は自らその身を大切にすること。
- 自己愛はンルシシズムであり、自己陶酔、うぬぼれのこと。
自愛は自分自身をそのままの自分自身として受け入れることであり、ほかの生命と同じように、自分自身を維持しようとする根本的な欲求を持っているが、自分自身にうっとりとする自己陶酔やうぬぼれはである自己愛は自らその身を大切にすることには繋がりません。それ故、自己愛はいつも不安と隣り合わせだと書いています。
しかし、多くの人は自愛も自己愛も合せ持っていて、それは、親子関係や結婚の時に多く表れやすいと言います。私を含めて多くの人が子供を理想的に育てようと執着しているだろうし、結婚相手にしても執着心はないとは言い切れないと思います。
人間は成長し他人との関係を結ぶために多くの物事を身に着けなければならなくなり、自分の外にあるものを身につけるとき、それを持っていない自分を「つまらないもの」と思ってしまいます。それらを身につければ身につけるほど目標も高くなってしまい自分がますますだめなものになっていくのだと言います。
それには、自分が求めるものを、自分なりのやり方で自分の潜在的な力を発展させ、実現することで、身軽になっていくことで自愛を得ることが出来ると書いています。
人間とはとてもやっかいだと思いながら読みました。
それ故、自分を愛することが出来て初めて人を愛することが出来ると言います。
私のように何も期待されず、ただいろいろ知りたいと思いで何かに取り組み、自分では出来ないと思っていたことがいつの間にか身についているという生き方をしてきたものにとっては、自己陶酔やうぬぼれを持つということは感じたこともありません。
これは期待されることもなく、子供時代を過ごしてきたからなのでしょうか。
スポンサーリンク
4 貨幣について
この章ではドイツのハイデマリー・シュヴェルマーと言う女性がお金なしの生活を実験したという話をから貨幣について書いています。
- 貨幣を使うと、知らない間に与え合うことになっている
- 貨幣は他人との信頼関係を造り出すために使うべき
- 貨幣は他人とのしがらみを断ち切るために使える
「貨幣は他人とのしがらみを断ち切るために使える」というのは、人間関係はどんなに親密で暖かい関係だと思っていても、ちょっとしたことで嫌気がさしてしまうことがあり、そんなときに「手切れ金」という使い方もあると書いています。
また、お金を必要としている人に払うという「有徳人」になるという懸命な方法も書いています。
5 自由について
- 自由とは、選択の自由のことではない
- 自由でいるためには、勇気が必要である
- あなたの人生の目的は、ほかの誰とも違っている
- 人生の目的に向かって進んでいるかどうかは、感じることが出来る
よい大学に入り、よい会社に入り、収入が高ければ幸せになれると信じている人はかなり多いと思うし、そのために自分の子供に勉強を無理強いしている人も多く、それを子供も信じている場合が多いと思います。
それは日本の社会では高い学歴が、高い社会的地位を得るための最良の道具だからと言いますが、それによって得たものが自由だとはいえないし、社会的地位が高いために失う自由も大きいのです。
それぞれの人が人生において幸せだと感じるものも違うし、自らの生き方を愛し、うらやむことのない生き方をしていることこそが自由なのだろうと私は思います。
6 夢の実現について
- 夢とは、人生の目的に向かう一里塚である
- 夢は肯定形ののイメージでしか表現できない
- 夢を実現する過程で得られる副産物が、あなたの糧となる
「夢とは人生の目的に向かう一里塚である」私は夢を見ることもなく流されて老年期にきてしまいましたが、(したいことはあってもいろいろな事情があり出来なかった)自分のやりたいことをずっとしてきたために現在は後悔することもなく、今でも好きなことして、前に向かって進んでいます。
新しいことをしたいという気持ちはありますが、やりたいことが多く、それほどの時間も残っていないと思うと現状を維持しながら進むほかはないと思っています。
人をうらやむことも、うぬぼれることもないのはそのような年齢なのかもしれないと思っています。
7 自己嫌悪について
- 「幸福」を手に入れようとすると、魂が憧れてしまう
- 自分がなぜ自分を嫌いなのか、その原因を考える
- 自己嫌悪は、自己の感覚の否定であるから、ある感覚が作動しなくなり、そこが盲点になる
- 自己嫌悪を乗り越え、自分を愛するようになることが、成長をもたらす
ここで言っていることは、育てられ方によって、「自分は悪い子だと思ってしまう」ことのようだが、憧れてしまうとか自己嫌悪に陥ると言うことには、「他の人は簡単にできるのに自分が劣っている」ことがあるのも大きいのではないかと思ってしまいました。
私は、成績は良かったのですが、引っ込み思案であったり、運動神経が鈍かったりして、それが出来る人に憧れた子供時代からある程度の年齢になるまでは、それが自己嫌悪の原因になっていました。
それらをすべて自分自身のこととして認められるまでにはかなりの年月を必要としたし、自分のしていることを他人から何を言われてもかまわないと思うことが出来るようになったとき、自己嫌悪から抜け出すことが出来ました。
自分は悪い子だと思ってしまうような育てられ方はしたことがなくても、人はそれなりの弱点を持っていることで、若いときには自己嫌悪を感じている人は多いと思います。
しかし、自分なりの生き方が見つかれば、それから抜け出すことも可能のような気もします。
8 成長について
- 成長とは生きる力の増大である
- 自分のやっている努力に意味があるかないか、感じることが大切
- 感覚を再生したいと願うことは大切
私は老年期に入っていますが、それでも日々いろいろと新しいことを学び、成長していると勝手に思い込んでいます。
悩み多い青春時代を過ごし、自分探しに悩みながらも、懸命に生きてきたと思えたとき、自然に自愛の心が芽生えていたのを感じることが出来ました。
体力の衰えは年々感じていますが、それにも増して様々な分野の本を読んで、それまで知らなかったことの多さを日々感じています。
知的欲求がなくなったとき、自分のやっている努力に意味があるかないか、感じるのだろうと思いなから読了しました。
『生きる技法』の感想
初めて読んだ安富氏の著書からは多くのことを学ぶことが出来ました。
私のような老齢の人に向けて書いているのではないと思いますが、それでもそれまで気が付かなかったことを学ぶことが出来ました。
特に「自立とは依存すること」は今まで思ってもみなかったことでした。
それに、私が若い頃から愛読していた「歎異抄」の考え方に影響を受けているようで、とても身近に感じることが出来ました。


